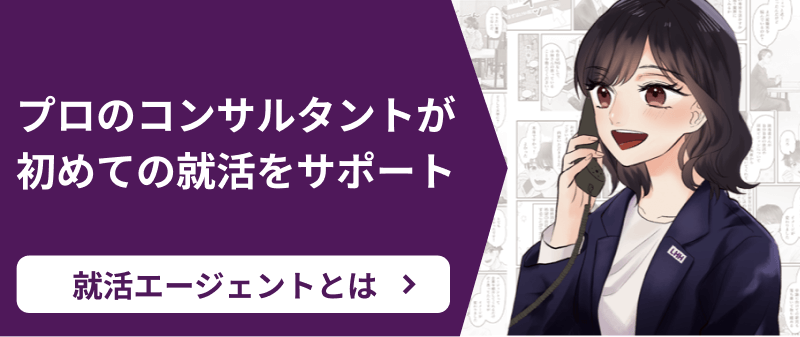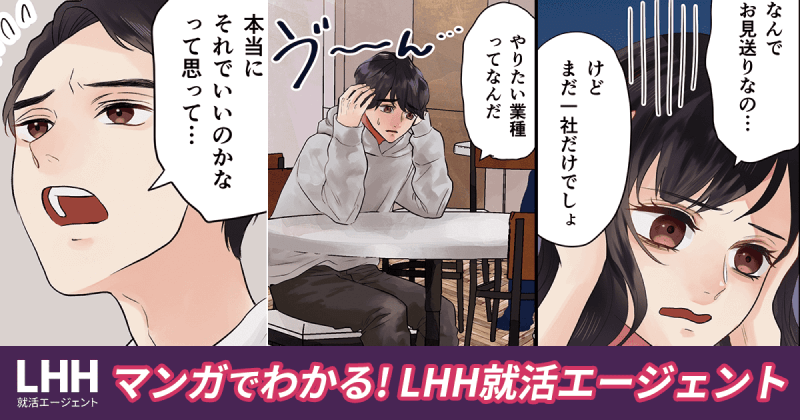#就活 #志望動機
就活の志望動機は、応募企業に対して自分の熱意や適性をアピールする大切な要素です。とはいえ、どのように自分の思いを言葉にすべきか困っている方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、志望動機に関して企業が注目しているポイントや書き方などを解説します。志望動機の例文も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
- 就活の志望動機から企業は何を見ているのか
- 【3ステップ】就活の志望動機の書き方
- 志望動機を書くときに押さえるべき4つのポイント
- 【例文】就活の志望動機の書き方
- 採用担当者に響く志望動機の作り方をLHHが徹底サポート
就活の志望動機から企業は何を見ているのか

企業が志望動機を知りたがるのは、「その就活生の価値観や適性が自社にマッチしているか」、「どれだけ熱心に自社へ入社したがっているか」を確認するためです。企業側としては、せっかく採用するからには自社で長く活躍できる人材を求めています。しっかりした志望動機があるか否かは、そのための判断材料のひとつです。
就活の軸と自社がマッチしているか
企業は、就活生がどのような価値観やビジョンを持って応募企業を選んでいるか、そしてその「就活の軸」が自社とマッチしているかを確認したいと考えています。企業がこの点を重視する理由は、就活の軸と企業の方向性が一致していないと、入社後のミスマッチが起こりやすいからです。
企業にはそれぞれ独自の社風やビジョンがあります。たとえば、革新的な事業に魅力を感じる就活生が伝統を重んじる保守的な企業に入社しても、考え方の違いから早期離職に至るリスクが高まります。企業はこうしたミスマッチを避けるために、就活生の志望動機をチェックします。
志望の熱意、優先度は高いのか
就活生の入社意欲の高さも、企業が志望動機から読み取ろうとする要素です。企業側としては、いくら優秀な就活生でも最終的に入社してくれないのでは内定を出す意味がありません。また、入社してもらえても、自社への熱意や共感がないのでは、業務で積極的な貢献を期待するのは難しいです。
基本的に志望動機には、その就活生が「応募先企業のどこに魅力を感じているのか」「入社後はどのように貢献したいと思っているのか」が書かれています。質のよい志望動機を書くためには、しっかりした企業研究が不可欠です。経験豊富な採用担当者には、他企業でも使っている志望動機はすぐに見破られます。企業は志望動機を通じて就活生の本気度や自社への理解度を把握し、内定を辞退する可能性が低く、入社後も長期的に活躍できる人材かどうかを見極めようとします。
【3ステップ】就活の志望動機の書き方
立派な志望動機を持っていても、それを相手へ効果的に伝えるためには一定のスキルやコツが必要です。志望動機を書く際は、以下の順番で自分の伝えたいことを記載しましょう。
STEP1. 魅力に感じたポイントをまず伝える
志望動機は「結論ファースト」で書くのがポイントです。例えば、「私が貴社を志望した理由は、~に魅力を感じたからです。」といった形で書き始めると良いでしょう。「~」の部分は、事業内容や経営方針、社風など、さまざまなことが考えられます。その企業の実態とは異なることを書かないようにするためには、企業研究が欠かせません。
いずれにせよ、結論から説明を開始することで、採用担当者が話の流れをすぐに把握しやすくなります。志望度が高い場合はいくつも理由が思い浮かぶかもしれませんが、文字数には限りがあるため、「その企業ならでは」の説得力や思いが最も伝わる理由に絞って書きましょう。
STEP2. なぜ魅力的だと感じたのか、根拠をもって理由を説明する
次に、企業のその要素に自分がなぜ魅力を感じたのか、具体的な根拠を書きます。たとえば、「チームワークを重んじる社風に惹かれました。」という言葉は、それ自体では根拠の説明になっていません。個人主義的な就活生にとって、その要素はマイナスにもなりえるからです。
そこで志望理由に深みや納得感を与えるために大切になるのが、「就活の軸」を絡めて書くことです。たとえば先の例なら、「学生時代にサークル活動を通して、チームで協力しながら目標を達成することにやりがいを感じるようになりました。」などと具体的なエピソードも絡めつつ、自分の価値観と企業の特性がマッチしていることを示しましょう。
STEP3. 自身の強みを生かしながら、どのように活躍・貢献できるかをアピールする
最後に、自分が入社後にどのように企業へ貢献できるか、自分の強みをアピールします。企業がお金をかけて従業員を雇うのは、コストに見合うだけのメリットをその人材に認めているからです。
したがって就活では、自分を雇ったら得すると企業に思ってもらえるように、性格面も含めた自分の長所やスキル、経験をアピールすることが欠かせません。大学で研究した知識、取得した資格、サークル活動やアルバイトから得たノウハウや教訓など、具体性に富んだ内容にするのが大切です。
志望動機を書くときに押さえるべき4つのポイント

何を伝えるべきか明確にしないまま志望動機を作成すると、企業に対する本気度や適性が伝わりにくくなります。そこで以下では、説得力のある志望動機を書くために押さえておきたい4つのポイントを解説します。
1. 就活の軸
志望動機の根幹となるのが「就活の軸」です。これは、あなたが仕事を選ぶうえで大切にしている価値観や優先事項を指します。まずは自己分析を行い、自分にとって「譲れないポイント」や「重視したいポイント」を整理しましょう。
たとえば、「人々の健康に貢献できる仕事がしたい」や「チームワークを大切にする企業で働きたい」といった就活の軸を持っていれば、それに基づいて応募先企業との接点を説明できるようになります。自己分析だけで就活の軸がはっきりしない場合は、OB・OGや周囲の就活生に尋ねて参考にしてみるのもおすすめです。
2. 自身の「強み」
志望動機では、「あなたがその企業に惹かれた理由」と同時に、「その企業があなたを採用するメリット」も示さなければなりません。強みを発揮できる環境で働くことは、自分のキャリアアップや充実感を得るためにも大切です。
この強みとしては、実務的な知識やスキル、資格だけでなく、忍耐力や協調性、リーダーシップのような性格的特性を挙げることもできます。「接客のアルバイトで培ったホスピタリティを生かし、お客様に寄り添った顧客サポートをしたいと思います。」など、自身の強みを入社後どのように役立てられるかを書きましょう。
3. 企業の魅力
事業内容や経営方針、社風など、企業のどこに魅力を感じたのかを明確に示すのもポイントです。この点が曖昧だと、「別に他の企業でもいいのではないか」と志望の本気度を疑われてしまいます。
たとえば、「業界内でいち早く○○に取り組んでいる貴社の先進性に惹かれました。」といった形で、その企業ならではの特色を踏まえて志望動機を述べると、しっかり下調べをしたうえで応募していると本気度をアピールできます。企業・業界研究や企業説明会への参加を通じて、その企業が持つ独自の魅力を掘り下げてみましょう。
4. 自身の就活の軸と強み、企業の接点
最後に、これまでに整理した「就活の軸」「強み」「企業の魅力」の接点ないしは整合性をチェックしましょう。これによって、あなたがなぜその企業を選んだのか、またどのように貢献できるのかを一貫性をもって伝えられます。逆に、それぞれがバラバラだと説得力に欠ける内容になってしまうため、注意が必要です。
【例文】就活の志望動機の書き方

上記のポイントを踏まえて、志望動機の例文を作成しました。参考にしてみてください。
【例文】
私が貴社を志望したのは、「顧客ファースト」をモットーに、きめ細やかな顧客サービスを提供している点に強く惹かれたからです。私は、お客様一人ひとりに寄り添う仕事をしたいと考えています。学生時代には、スーパーでアルバイトを行い、日々さまざまなニーズを持つお客様に接客してきました。ときにはクレーム対応に苦労することもありましたが、それだけに「いつもありがとう」とお客様から温かい言葉をかけていただけると強い喜びを感じました。
貴社はデータ分析なども活用し、お客様の隠れたニーズにも対応できるように会社全体で努めていると伺いました。お客様のニーズを考え、応えることは、お客様一人ひとりに寄り添う仕事につながると考えています。貴社に入社した暁には、アルバイトで培ったお客様一人ひとりに寄り添った姿勢や忍耐力を生かし、カスタマーサポート業務で貢献し、顧客満足度をさらに高めたいと考えています。
採用担当者に響く志望動機の作り方をLHHが徹底サポート
志望動機は、応募先の企業にあなたの価値観・意欲・強みを伝える重要な要素です。単に「入りたい」と伝えるのではなく、自己分析や企業研究を通じて、自分の強みや就活の軸を明確にし、「なぜこの企業なのか」「どのように貢献できるのか」を具体的に伝えることが求められます。
「自分の強みをどう言語化すればいいのか分からない」「企業ごとに適した表現が思いつかない」と悩まれている方はLHH就活エージェントにご相談ください。

LHH就活エージェントでは、経験豊富なコンサルタントがキャリアカウンセリングを実施し、模擬面接や個別アドバイスを通じて、あなたの強みを最大限に引き出すサポートを行います。自己PRや志望動機のブラッシュアップ、想定質問の対策など、面接成功に向けた実践的なアドバイスを提供。
「説得力のある志望動機を作りたい」「企業にしっかりアピールできる内容にしたい」と考えている方は、ぜひLHH就活エージェントにご相談ください。プロのサポートを受けながら、納得のいく志望動機を完成させ、内定獲得を目指しましょう。